一閑張・一閑張り・一貫張りの情報満載
侘びとはつつましく、質素なものにこそ趣があると感じること。一方、寂びとは時間の経過にって現れる美しさを指します。当に、一閑張り/一貫張りにふさわしい表現ではないでしょうか?そんな魅力を伝え、広めてゆく為に、様々な情報を発信しております。
一閑張り/一貫張り
一閑張りの現状「真偽顚倒し玉石混淆す」
最近では和紙の上から和柄の布、古布等を貼った買い物かごが主流となっているようで、中には和紙の上に柿渋も塗布することなく、いきなり布を貼った物まで登場し、その定義が、「一閑張りとは竹籠の上に和紙を貼り重ね、上に布を貼って仕上げた物」と新説を唱えられております。和紙を貼り重ねるのは、布を貼った時に、籠の凸凹を隔す為だそうです。もう全く、一閑張りの魅力を理解できていないんですね。そういう方が、堂々と一閑張り教室を開催され、それが、メディアで紹介され、誤った情報が拡散している状況すらあります。一閑張り/一貫張りが注目され始めて、かれこれ四半世紀が経ち、一閑張り教室の先生も、子、孫、ひ孫と、ドンドン拡がってますから、そういう方が生まれても不思議では無いかも知れません。更に、悪いことに全面に布を貼った籠バックを一閑張りだと勘違いされている方も多いようで、この流れが進んでいくと、一閑張りが本来の姿から異なった文化になりそうで、少々由々しき状況です。料理に例えるなら、チキンライスを卵で包んでオムライスに成る様なものでしょうか。更に、何かと話題の多い故郷納税返礼品にも多数登場してきます。伝統工芸品に指定されている香川県なら話しは解りますが、何も関係ない市町村で、しかも、全面布を張った物がゾロゾロと。あのなんでもありで、兎角問題の多い泉佐野市の返礼品にも堂々と登場します。住人の手づくり作家が造れば、地元の名産品になるって事でしょうか?しかも納税額が10万円越えですからね。方や手作り品販売サイトでは、趣味で始められた初心者の方が作られたら作品が数百円でアップされてます。かと思えばその一方で、飛来一閑直系として家元を名乗り、拘りの世界を全面に打ち出して活動されている方もおられます。千家十職一閑張細工師の飛来一閑秘伝は関係ないと思うんですがね。当に「真偽顚倒し玉石混淆す」状態です。
一閑張/一閑張り/一貫張りの語源由来と技法
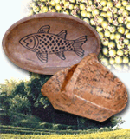
①一閑張(一閑張り細工)と飛来一閑
一閑張り/一貫張りの由来については諸説あります。中でも一番有力な説といわれているのが飛来一閑説ですが、元々、漆器の技法の一つに紙胎と呼ばれる技法があり、特に飛来一閑の物が優れていたので、一閑塗と呼ばれたようです。方や庶民生活から生まれた閑張り(ひまはり)が、京都の茶文化への憧れから一閑張りとも呼ばれる様になったのではないでしょうか?飛来一閑が伝えたとされる物は、紙漆細工と呼ばれる漆工芸品の一種で、素地に和紙を貼り、漆で仕上げた紙胎漆器や張抜きと言われるものを指します。特に彼の作風が優れていたので一閑塗りと呼ばれ、やがて一閑塗と張抜きと紙漆細工が合わさって、一閑張細工と呼ばれ、紙漆細工の代名詞になった様です。現代風に言えば、当時の漆器のブランド品というところでしょうかね。
②紙漆細工の紙胎・張抜と飛来一閑張細工
上記の様に、中国の明からの渡来人で飛来一閑が伝えた技法という説が有力ですが、その技法にも諸説があります。そもそも以前から漆器の技法として紙胎漆器はありました。漆器と言えば木製が一般的ですが、実はその素地に何を使うかによって異なり、〇胎漆器と呼ばれ、〇の中に何が入るかによって変わってきます。素地に和紙を貼り重ね、上から漆を塗って仕上げる技法が紙胎漆器で、木地に塗った物は木胎漆器と呼ぶのが正しい呼び方となります。他に陶器を使った陶胎漆器、竹籠を使った物は藍胎(らんたい)漆器と呼ばれています。其の中でも、特に彼の紙胎漆器技法が優れていたから、茶道の千宗旦が愛用して一閑塗と呼ばれたと言われています。漆器の世界は分業制で、素地師、塗師、加飾師に分かれますが、彼は素地から作ったのではないでしょか?その後、張抜きと呼ばれる中の木型を抜く技法も加わり、一閑塗と張抜きの二つの言葉から一閑張と呼ばれ、更には紙漆細工と合わせて一閑張細工と呼ばれるようになったと推測されます。漆器ですから、当然ながら柿渋は使用されず、現在広く一般的に一閑張りと呼ばれているものとは異なります。今では漆器は木胎漆器が一般的ですが、現在でも飛来一閑の流れを汲む第16代を名乗る女性が、京都でこの伝統的技法でモノ造りを続けておられます。
③飛来一閑の一閑張細工の特徴と京漆器
そもそも、飛来一閑の一閑張細工なる物の特徴とは如何なる物だったのでしょうか?ネット上でも、飛来一閑に関する情報は一杯ありますが、今一つはっきりしませんが、現在でも初代飛来一閑の流れを汲む第16代飛来一閑さんによると「木地に和紙を張り、その上に一回だけ漆を塗る手法で、棗、香合等の茶器が主体。ざんぐり(大まかで風趣な趣がある素朴な肌合い)を、千宗旦に好まれたのではないか?とのお話です。やはり、どうやら紙胎漆器だと言う事です。当時の茶の湯の世界では、京漆器が有名で主流でした。その特徴は、他産地の漆器と異なり生地が薄くて軽いのが特徴で、その上に黒漆器を塗り重ね、最後に蒔絵等の装飾をした華やかな物でした。そんな環境の中で、飛来一閑の紙胎漆器の素朴な風合いが受け、一閑塗と呼ばれて好まれたのではないでしょうか?やがて、張抜きと呼ばれる手法にも拡がり、一閑塗と張抜きの言葉が合わさって、一閑張細工と呼ばれる様になったのでしょう。後に千家十職に選ばれますが、京漆器ではすでに塗師として中村宗哲がいましたから、区分として一閑張細工師飛来一閑とされたのでゃないでしょうか。この様に、一閑張細工は茶の湯と言う狭い世界で楽しまれた物だと思います。参考までに、骨董品の世界では果たしてどうか?一閑張りでネット検索すると、茶器の棗等が出てきますが、代何代飛来一閑作○○と表現され、一閑張りと言う表現は見当たりません。④閑張りと一閑張り/一貫張り
昔、農家では、竹籠やザルに和紙を張り、上から柿渋を塗った物を作って日常生活で使用していました。特に農閑期などの閑な時に作る事から、閑張り(ひまはり)と呼ばれたようです。そもそもが養蚕や製茶様に使用されていたものが、一般の日用品にも利用されるようになり、古くなったザルやカゴ等が再利用されるようになった、まさに、これぞリサイクルですよね。更にこれを繰り返す内に柿渋の力で強度が増していき、一貫目の重さにも耐えられるって事で一貫張りと呼ばれることになったという説があります。
その後、古くなった木製の家具等にも範囲が広がっていったようです。
ちなみに、夏目漱石の有名な小説「坊ちゃん」の中に、一閑張り机なるものが登場するように、特に四国で一貫張りとして広がった様です。また、江戸川乱歩の作品の中にも一閑張り机が登場します。

⑤張抜き/張り子/張りぼて
木枠や粘土を固めた物の上から和紙を貼り合わせ、胡紛に膠を加えた物を塗り重ねて下地とし、固めてから中を抜き、最後に彩色を施す技法で、民芸品とか祭事などに利用されることが多くありました。張り子の虎、達磨、起き上がりこぼし、お面などがありますが、地方によっては一閑張りと呼ばれています。これは、漆器の張抜きと同じ手法ですから、その影響で一閑張りと呼ばれるようになったのではないでしょうか?有名な唐津くんちの曳山もこの製法ですが、漆で仕上がられた乾漆造と言われ、こちらは正式に、一閑張りとして文化庁の民俗文化財に指定されています。又、地元では、漆の一閑張りと呼ばれているようで、わざわざ、漆に拘るってことは、普通の一閑張りには、漆は使用しないってことの裏返しではないでしょうか?一閑張りにも諸物あり/
語源と由来は別です
但し、語源と由来は異なります。由来としては諸説り、一閑張りには何種類かあるってことだと思います。今更、歴史を元に戻すことは出来ませんが、伝統工芸を名乗る以上は、その精神から原点に立ち返る必要があると思います。
少々乱暴にまとめると、
①柿渋を使った日用品で、一閑張り又は一貫張りと呼ぶ。
②漆を使った茶器などの嗜好品で紙漆細工の一閑張細工と呼ぶ。
③乾膠の民芸品で、乾漆の張抜き及び乾漆の張り子と呼ぶ。
これが、正解なのでは無いでしょうか。
尚、後述する香川県や丸亀市の伝統工芸品指定の見解も含め、解り易い様に整理して簡単な表にしてみました。
一閑張り/一貫張り 一覧表
| 生地 基材 | 表面 素材 |
作風・作り方 | 仕上げ材 | |
| 飛来一閑説 一閑張細工 |
木型 | 和紙 | 張抜き紙胎 木型に和紙を貼り重ね、完成後に中の木型を取り出す |
漆 |
| 藍胎漆器紙胎漆器と一貫張が混同された 一閑張 |
木型 竹籠 |
和紙 | 木型竹籠に和紙を張り重ねる | 漆 柿渋 |
| 閑張り (ひまはり)説 一閑張り |
竹籠 | 和紙 古書 |
竹籠に和紙(古書)を貼り重ねる | 柿渋 |
| 讃岐一貫張 一貫張り |
竹籠 | 和紙 古書 |
竹籠に和紙(古書)を貼り重ねる | 柿渋 |
| 張り子 乾漆張抜き |
竹籠 麻布 | 粘土 和紙 | 竹細工に和紙と麻布 粘土を塗貼り重ねる |
漆 膠 |
以上、取り敢えず、現時点での私的見解とさせて頂きます。
一閑張り/一貫張りと伝統的工芸品

①一閑張り・一貫張りと香川県/丸亀市
前にも触れましたが、一閑張り/一貫張りは特に四国が有名ですね。今回、訳あって、再度一閑張りについて色々と調べてみたところ、思わぬ発見がありました。なんと香川県では、一閑張り・一貫張りと併記して、県の伝統的工芸品に指定されているのです。しかも昭和62年ですから1987年と随分と古い話しです。どうして今まで気づかなかったのでしょうか?大いに反省すべきところです。項目は木工品として、「竹かごや木型に和紙を張り合わせ、柿渋を塗り重ねたもの」となっていて、漆は記載去れていません。漆細工は香川漆器の項目になっています。由来は、先に触れた閑張りと同じですが、「一つ閑が出来たから張るか」ってことから一閑張りと呼ばれたとなっており、閑張りから一閑張りへと変化したという説とは微妙に異なりますが状況は同じですね。ところが同じ香川県内の丸亀市も独自に伝統的工芸品に指定しているのですが、こちらは、なんと一貫張となっており、一閑張りの表記はありません。由来については、讃岐生まれの弘法大師が柿渋塗りを持ち帰ったことに始まる1200年の歴史を誇る讃岐一貫張となっています。現在でも六代目万洪庵一貫斎と名乗る方が伝統的な作風で頑張っておられます。1200年の歴史と弘法大師様ですからね。400年の歴史の飛来一閑とは格が違いますね。まあこれで、チョッと話しがややこしくなってきました。「一閑(ひとひま)張りから一閑張りと呼ばれ、やがて一貫張りになった」説に疑問符がついてきます。
下記の丸亀市公式HPを参考に御覧ください。

②一閑張り家元 飛来一閑泉王子家の謎と愛媛県松山市
最近、積極的に活動されている一閑張り家元飛来一閑泉王子家14代なる方がおられます。立派なホームページも立ち上げられ、京都西陣で400年の歴史と伝統を誇っておられます。初代飛来一閑家から分派されたとの事ですが、2代目は創作活動は行なわず、3代目が復活させたというのが定説です。更に、泉王子家とは?と、ネットで必死になって探しても情報はありません。そもそも、飛来一閑が分派したという事実すらありません。飛来一閑家については系図がハッキリしてますが、泉王子家にはありません。本来、家元という言葉は、伝統芸能・武道の世界で使われますが、伝統工芸の世界では使われません。謎だらけですが、遂に発見した!13代を名乗る方が、愛媛県松山市で活動されていたようです。どうやら、愛媛県の伝統的工芸品の「張り子の姫だるま」を造っておられたようです。作品が、「一閑張りの張り子」として、画像の人形と共に、下記のサイトで紹介されています。
http://www.asahi-net.or.jp/~SA9S-HND/agal-972-1.html
一閑張りの張り子
松山市内に一閑張り(いっかんばり)の手法で、張り子の「だるま」をはじめ「干支(えと)の張り子」「面」などを作っている泉王子(せんおうじ)治さんがいられます。製作をはじめてから25年余になります。掲載の作品のように、すべて泉王子流のデザインで作られています。昭和47年頃に、高知県の人から「坊さんかんざし」の張り子の原形復元を依頼され、半年かかりで完成し好評を得ました。それがもとで郷土玩具を作るようになりました。松山に住んでいるのだから、高知のものでなく「松山のもの」を作ろうと、「だるま」を作り始め、また、松山に昭和初期まで「面」があったことを知り、年寄りの話しを聞いて「お多福、ひょっとこ、カッパ」などの面を復元しました。
最後に、ご本人が自己紹介されております。
大正15年生まれ。愛知県出身。幼くして父と死別。10才にして近所の一閑張り職人の泉王子家に弟子入りしました。24才のとき、全国の寺社の彫刻を見てまわり、放浪の旅を続け、40才のとき松山い腰を落ちつけて、それを機に、山田姓の本命から、13代目の泉王子(飛来一閑正伝13世)の名前を継ぎ、この地で一閑張りの仕事を続けています。
制作者:泉王子 治
愛知県出身とのことで愛知県で情報を探したところ、一閑張が、漆工芸品として県の伝統工芸品として認定されていました。しかし、古い歴史は無く、昭和に入ってから、三河漆の発展の為に始まったもので、地元の小原和紙を使った一閑塗りをした紙胎漆器と定義されています。やはり、これが紙漆細工の一閑張細工だと思います。残念ながら、やはり泉王子家の名前も出てきません。
詳細は下記のhpを御覧ください。
https://www.pref.aichi.jp/sangyoshinko/densan/412.html
どうも、京都とは全く縁のない、しかも飛来一閑とは関係のない、張り子職人の様に思えるのですが・・・?
取り敢えず、コメントは避けて、事実のみを紹介しておきます。
このページの先頭へ
一閑張り机の謎?一閑張りの家具

「「 あの泥棒が羨ましい」二人のあいだにこんな言葉がかわされるほど、そのころは窮迫していた。場末の貧弱な下駄屋の二階の、ただひと間しかない六畳に、一閑張りの破れ机を二つならべて、松村武(たけし)とこの私とが、変な空想ばかりたくましくして、ゴロゴロしていたころのお話である。もうなにもかも行き詰まってしまって、動きの取れなかった二人は、ちょうどそのころ世間を騒がせていた、大泥棒の巧みなやり口を羨むような、さもしい心持になっていた。」破れ机と表現されてますから、紙が張られていることには間違いはありませんが、この場面背景から察するところでは、とても高級品とは考えられません。漆塗りの漆器では無い様です。引き続き、謎解きに挑戦です。
一閑張り・一貫張りの作り方
①竹籠を用意
本来なら竹籠を編むところから始めたいところですが、まずは市販の竹籠を用意しましょう。最近では100円ショップでも手に入りますが、ネットでも数多く販売されています。凝った複雑なデザインの物は紙を貼り難いので、始めは平らなザルなどからがお勧めです。②和紙を貼る
使用する糊については特に拘る必要はありません。一般的な事務用や障子糊を水で薄めて使用しますが、木工用ボンドを少量混ぜて使用すれば強度がまして有効的です。③乾燥
接待和紙を貼り終えたら十分に乾燥させてください。乾燥が不十分で柿渋をぬると、乾いた部分と塗れた状態の部分で斑になりますので、注意が必要です。④柿渋を塗る
十分に乾燥させたら、いよいよ柿渋を塗ります。一般的には刷毛を使いますが、カゴが小さくて塗り難い場合や、和紙が柔らかくて刷毛で塗ると毛羽が気になる場合には指につけて軽く叩き込む様にする技法もあります。使用する柿渋は無臭タイプをお勧めします。臭いのきついタイプは室内作業には不向きです。⑤乾燥
乾燥させれば完成です。更に、ここから経時変化で徐々に発色していきますから、独特の色のうつろいを見るのも、一閑張りの楽しみ方の一つです。なお、光沢ですが、使用する和紙の材質などによって微妙に変わってきます。光沢がないなあと感じた時は食用油で仕上げるのも一つの方法です。また、冬の乾燥時にひび割れを起こす場合もありますが、そんな時も食用オイルのご使用をお勧めします。⑥オリジナル性
上張りに墨で書かれた古文書を利用すると、墨の文字の色が柿渋と重なって独特の色合いになります。最初に一閑張りが人気になるきっかけはこの独特の雰囲気が要因でした。又、色紙を利用すれば、それぞれが独特のカラーに変化して楽しいですね。その他好みの絵柄の和紙を貼り付けたりしたオリジナルな作風創りが広がっていきました。最近では古布などの布を貼り付けた買い物かごが人気の様で、ネット上でも多く見られ、中にはこれが一閑張りだと勘違いされてる方もおられるようです。
オリジナルなモノ創りを否定するわけではありませんが、伝統工芸を名乗りるには、一定の要素を満たす必要があると思います。
全面を布張りにしたり、柄和紙で仕上げた作品は、一閑張りとは言えないと思います。
ましてや、仕上げに漆も柿渋を塗らないでは、もう完全に別物になっていると言わざるを得ません。一閑張りとは何か?その魅力は何処にあるのか?
もう一度、原点に帰って考えて頂いたと思います。
このページの先頭へ
一閑張りと五感張り

五感張りとは?
柿渋一閑張りの歴史/文化/精神を大切に守り引き継ぎながらも、新しいモノ創りで世界を拡げて行くために、当に人間の五感で楽しめるモノ創りを五感張りとなずけました。例えば上からカラフルな布等を貼り付ければ現代風の作風になります。又一閑張りの竹籠の代わりにダンボール・厚紙を利用すればフランスの伝統的な民芸品であるカルトナージュ風の作品になります。急激なネット化が進み、アマゾンなどネット通販での買い物が増えていますが、今回のコロナ禍で今後益々急速に増加することが予想され、それにつれて不要なダンボール箱が身の周りにあふれかえることになります。それらを再利用して収納容器などを作ってエコな循環型社会の実現を体感しましょう。ポリ袋の有料化など、脱プラ・断プラの流れが本格化し始めています。
一閑&五感
柿渋一閑張りと五感張りをセットにして広げていく為にブランドを立ち上げました。それが一閑&五感です。一閑張りと五感張りの間に境界線はありません。伝統としての一閑張りの精神を大切にしながら時代に合った新しい想像の世界を拡げる為に、一閑&五感のブランドで世界観を広めてゆきたいとい思います。全国の一閑張り・一貫張り教室工房
一閑張り/一貫張りは全国的な広がりを見せています。全国の一閑張り教室・工房を地域別に一覧表にしております。
お近くの教室、工房を探して一度体験されてはいかがでしょうか.
また、近隣でお探しの方に情報を発信するために、お知らせ頂ければと思います。
一閑張り教室一覧へはこちらからどうぞ
一閑張り・一貫張りと五感張り作品集
 |
||
 |
 |
このページの先頭へ
一閑張りと和紙について
和紙は一閑張りになくてはならない存在です。全国の和紙産地一覧です。
| 岩手県 | 東山和紙 | 成島紙 | |
| 宮城県 | 白石和紙 | 柳生和紙 | 丸森紙 |
| 秋田県 | 十文字和紙 | ||
| 山形県 | 深山紙 | 高松和紙 | 長沢和紙 |
| 築山和紙 | |||
| 福島県 | 福島和紙 | 遠野和紙 | 上川崎和紙 |
| 山舟生和紙 | 野老沢和紙 | 海老根和紙 | |
| 茨城県 | 西ノ内和紙 | ||
| 栃木県 | 程村紙 | 烏山和紙 | |
| 群馬県 | 桐生和紙 | ||
| 埼玉県 | 小川和紙 | 細川紙 | |
| 山梨県 | 西嶋和紙 | 市川和紙 | |
| 東京都 | 軍道紙 | ||
| 新潟県 | 小国和紙 | 越後和紙 | 小出紙 |
| 富山県 | 越中和紙 | 八尾和紙 | 五箇山紙 |
| 蛭谷紙 | |||
| 石川県 | 二股和紙 | 加賀和紙 | 加賀雁皮紙 |
| 福井県 | 越前和紙 | 若狭和紙 | |
| 長野県 | 内山紙 | 松崎和紙 | 立岩紙 |
| 岐阜県 | 美濃和紙 | 山中和紙 | 飛騨紙 |
| 静岡県 | 駿河紙 | 横野紙 | 駿河柚野紙 |
| 修善寺紙 | |||
| 愛知県 | 小原紙 | 森下紙 | |
| 三重県 | 伊勢和紙 | 深野和紙 | |
| 滋賀県 | 桐生紙 | 江州雁皮紙 | 揉唐紙 |
| 京都府 | 黒谷和紙 | 丹後和紙 | |
| 大阪府 | 和泉和紙 | ||
| 兵庫県 | 杉原紙 | 名塩和紙 | |
| 奈良県 | 國晒紙 | 吉野紙 | |
| 和歌山県 | 保田紙 | 古沢紙 | 高野紙 |
| 鳥取県 | 因州和紙 | ||
| 島根県 | 石州和紙 | 出雲和紙 | 勝地和紙 |
| 岡山県 | 備中和紙 | 高尾和紙 | 津山箔合紙 |
| 横野和紙 | 神代和紙 | ||
| 広島県 | 大竹和紙 | 木野川紙 | |
| 山口県 | 徳地和紙 | ||
| 徳島県 | 阿波和紙 | ||
| 愛媛県 | 伊予和紙 | 大洲和紙 | 周桑和紙 |
| 高知県 | 土佐和紙 | 大濱紙 | 土佐清澄紙 |
| 福岡県 | 八女和紙 | 筑後和紙 | |
| 佐賀県 | 名尾和紙 | 重橋和紙 | 唐津和紙 |
| 熊本県 | 宮地和紙 | ||
| 大分県 | 竹田和紙 | 弥生和紙 | 佐伯紙 |
| 宮崎県 | 穂北和紙 | 美々津紙 | |
| 鹿児島県 | 蒲生和紙 | ||
| 沖縄県 | 琉球紙 | 芭蕉紙 | 月桃紙 |
一閑張りには本粋無臭柿渋柿多冨がお勧め
和紙と柿渋は必需品です。柿渋をお求めなら完全無臭の本粋柿渋柿多冨がお勧めです。
お求めはこちらからどうぞ
このページの先頭へ
サイト案内
TOPページ
柿渋の販売
染料としての柿渋
塗料としての柿渋
和紙と柿渋(一閑張り)
柿渋ギャラリー/工房
柿渋ネットショップ街
柿渋染めマスク「福面」
柿渋でSDGs
柿渋雑学集豆知識
柿渋に関するQ&A
運営会社案内
プランニング&ネットワーク株式会社 柿渋プラネット
大阪市中央区久太郎町1-9-26
コンタクト
営業時間:10~16時
日祭日休業
お問合せ:テレワーク推進の為、メール・FAXにてお願い致します。尚、TELは専用携帯番号宛にお願い致します
メール:
kakitafu〇kakishibu-planet.co.jp
迷惑メール対策をおこなっております。お手数ですが〇を@に変えて送信願います。
fax:06-7739-5388
tel:080-6333-4803
サイトマップ
許可無く転写・複製・転記しないようにお願い致します。
Copyright(C)柿渋プラネット All Rights Reserved